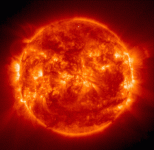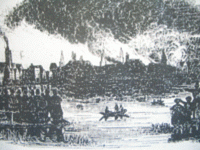天気のことわざいろいろ
「飛行機雲が現れると曇りか雨」
飛行機雲には、エンジンの排気ガス内の微粒子に水蒸気がついて雲になる 場合と、翼の端で気圧が下がり空気が冷えて雲になる場合の2種類がある。 いずれも天気が多湿の場合にできるので、カラッとした晴れは望めない。
「北東の風は天気が悪く冷たい雨が降る」
北方にある高気圧の影響で関東地方などに吹く冷たい北東風や、梅雨時 の三陸沿岸に吹くヤマセと呼ばれる冷湿の北東風は、いずれも冷たい雨 を降らせる。北東風が悪天候をもたらすという天気のことわざは、古く からギリシャや中国にもあった。
「星がまたたくと風が強くなる」
星がまたたくのは、密度の異なる空気が上空を横切るごとに地上に届く 光の強さや色が変化するためである。つまり、こういう日の上空では、 強い風が吹いているということだ。翌日になって太陽が昇ると地面が 暖められて上昇気流が発生し、上空の強い風が地上に降りてくる。
「流れ星多ければ日照り続く」
ヨーロッパで流れ星が多く見える年には、パリの冬は異常低温となって いる。日本でもたくさんの流れ星が見えた年の前年と翌年は干ばつが 多く、翌年は冬の気温が低くなる傾向にあるといわれている。
「冬の雷は雪起こし、春の雷は雪明け」
「雪起こし」は日本海側で冬にとどろく雷のことをいう。これは高さ6km もある積乱雲のしわざで、やがて大雪を降らすのでこの名がある。春の雷 は寒冷前線の通過とともに発生するので、その冬最後の大雪を降らせ、 やがて明るい春がやってくるという知らせである。
「小春日和が続く年は大雪。青山に雪が降ると次の冬は暖かい」
11月ごろの初冬の暖かい晴天のことを「小春日和」という。このような 日が続くと北極地方では寒気が蓄積されているわけで、この強い寒気は やがて真冬に日本付近に南下して大雪を降らせることになる。逆にまだ 山が青い秋のうちに寒気が南下して雪が降ってしまうと冬に寒気がなく なって暖冬になることが多いといわれている。
「クモの巣に夜露がかかると天気が良い」
クモの巣に夜露がかかるということは、これは湿度が高く夜間から未明 に気温が下がったことを示している。夜中に気温が下がるのは、風がなく、 空に雲がほとんどないないために起こる放射冷却によるものなので、 翌日はたいてい晴れる。真夏の晴れた朝には、草や屋根がびっしょりと 濡れていることがよくある。
「茶碗の飯粒がきれいにとれるときは雨」
高気圧が張り出して乾燥してくると、ご飯粒が乾いてくっつきやすくなる のでとれにくくなる。反対に低気圧が近づいて湿度が高くなると瀬戸物の 茶碗から離れやすく、きれいにとれるというわけである。
「煙が真上に昇ると天気が良く、横になびくと雨」
高気圧に覆われた晴れの空は、冷え込んで地面近くの空気は静かによど んでいる。このようなときは煙は真上に昇る。また、低気圧が近づいて 上空の風が強くなると、煙は横になびくようになる。