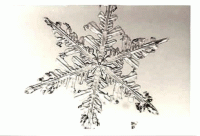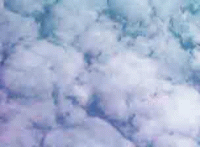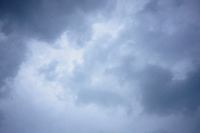雲の種類を大きく分類すると、10種類の基本形となる。
高層に現れる雲
巻雲(けんうん)
和名:すじぐも
俗名例:羽雲、馬尾雲(ばびうん)、真錦雲、つりばり雲、房雲

「繊維状をした繊細な、はなればなれの雲で、一般に白色で羽毛状、
かぎ形、直線状の形となることが多い。あるいは白かほとんど白の
かたまりまたは細い帯の形をした雲で、毛状をしているかまたは
絹のような光沢をもっている」(気象業務法施工令の定義)
青空に白くハケでさっとなでたように見える形の雲。
雲は氷晶の
集まりで、太陽の方向にある濃い雲は、やや灰色がかって見えたり、
太陽の輪郭をぼかすこともある。
巻積雲(けんせきうん)
和名:まだらぐも
俗名例:さば雲、うろこ雲、うね雲、レース雲

「小さい白色の片(部分的には繊維構造が見えることもある)が
群をなし、うろこ状またはさざ波状の形をなした雲で、陰影はなく
一般に白色に見える場合が多い。大部分の雲片の見かけの幅は一度
未満である」(気象業務法施工令の定義)
見かけの幅が一度未満というのは、一つひとつの雲の塊りが小さいということ。空に白い小石を敷き詰めたような、あるいは池や湖のさざ波のような雲。うろこ雲、いわし雲などとも呼ばれる。
氷の結晶でできていて、単独に発生する場合もあるが、巻雲や巻層運から変化したり、巻雲や
巻層雲と同時に現れることが多い。
巻層雲(けんそううん)
和名:うすぐも
俗名例:幕雲

「薄い白っぽいベールのような層状の雲で陰影はなく、全天をおおう
ことが多く、普通日のかさ、月のかさを生ずる」(気象業務法施工令
の定義)
高い空に一面、白っぽいグレーの布をおおったように見える。
巻層雲は氷の結晶の集まりでできているため、雲が太陽や月にかかる
と暈(かさ)が現れる。巻層雲は空の一部に出現していても、やがて
全天に広がることが多い。そうなると天候悪化の兆しである。
中層に現れる雲
高積雲(こうせきうん)
和名:むらくも
俗名例:ひつじ雲、だんだら雲、石垣雲、うね雲
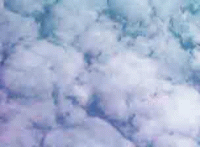
「小さなかたまりが群をなし、まだら状または数本の並んだ帯状の雲で、
一般に白色または灰色で普通影がある。雲片は部分的に毛状をしている
こともある。規則的に並んだ雲片の見かけの幅は一度から五度までの
間にあるのが普通である」(気象業務法施工令の定義)
羊の群のように見える雲で、色は純白から暗い灰色までさまざま。波のような形になったり、レンズのような形でポッカリ浮かんでいることもある。
高積雲は、普通は水粒でできているが、非常に低温の場合は、雲の一部が氷の結晶となることもある。
高層雲(こうそううん)
和名:おぼろぐも
俗名例:幕雲

「灰色の層状の雲で、全天をおおうことが多く、厚い巻層雲に似ている
が日のかさ、月のかさを生じない。この雲のうすい部分ではちょうど
すりガラスを通して見るようにぼんやりと太陽の存在がわかる」(気象
業務法施工令の定義)
多くは灰色で明るいものから暗いものまである。
高層雲は水粒と氷の結晶が集まってできている雲で、雲の中には雨粒や雪片が含まれて
いることもある。
高層雲が出ると雨が近いとみてよい。
乱層雲(らんそううん)
和名:あまぐも
俗名例:くろ雲、流れ雲、乱れ雲
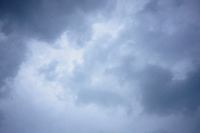
「ほとんど一様でむらの少ない暗灰色の層状の雲で、全天をおおい雨
または雪を降らせることが多い。この雲のいずれの部分も太陽をかくし
てしまうほど厚い。低いちぎれ雲がこの雲の下に発生することが多い」
(気象業務法施工令の定義)
雨を降らせる雲で、輪郭がはっきりしない、いわゆる雨雲が乱層雲で
ある。厚みをもった雲なので、太陽光線を通さず黒や灰色になる。
水粒、雨粒、氷の結晶や雪片などが混合したものでできている。
低層に現れる雲
層積雲(そうせきうん)
和名:くもりぐも
俗名例:土手雲、冬曇り雲、寝雲、うね雲

「大きなかたまりが群をなし層または、まだら状、うね状となっている雲で
白色または灰色に見えることが多い。この雲には毛状の外観はない。
規則的に並んだ雲片の大部分は見かけ上五度以上の幅をもっている」
(気象業務法施工令の定義)
いわゆる曇り雲。堤防のような雲がいくえにも規則的に重なって、
空の一部または全天に広がって現れる。
普通、層積雲は水粒の集まりで太陽がまったく見えないほど層が厚いことも、太陽の位置がわかるくら
い層が薄いこともある。
雲のあいだから太陽または青空が見えるときは、一般的には天気が穏やかであるとみてよい。
層雲(そううん)
和名:きりぐも
俗名例:かすみ雲

「灰色の一様な層の雲で霧に似ている。不規則にちぎれている場合も
ある。霧雨、細氷、霧雪(むせつ)が降ることがある。この雲を通して
太陽が見えるときはその輪郭がはっきりわかる。非常に低温の場合を
除いては、かさはできない」(気象業務法施工令の定義)
地表に近い低い所に現れる雲で、ときには高層ビルにかかることもある。
これが地上まで降りてくると霧になる。
山の谷にかかる霧も層雲で、登山やハイキングなどで経験する場合は、これをガスという。
極寒地では層雲が凍り、氷の結晶になって降ってくるが、これをダイヤモンドダストという。
層雲は普通は水粒でできていて、雨粒が非常に小さく、霧のような雨が降るときの雲は層雲、雨粒の大きい雨は乱層雲である。
層雲が発生しているときは、大気の状態が穏やかであることを示しているといわれる。
積雲(せきうん)
和名:つみぐも
俗名例:錦雲、浮島雲、ひる雲、入道雲、太郎雲

「垂直に発達したはなればなれの厚い雲で、その上面はドームの形を
して隆起しているが、底はほとんど水平である。この雲に光が射す場合
は明暗の対象が強い。積雲はちぎれた形の雲片になっていることがある」
(気象業務法施工令の定義)
積雲は主に水粒の集まりでできているが、雨粒や雪片などが含まれて
いることがある。
積雲は上昇気流によって垂直方向に発達し、さまざまな高さの雲に成長する。平たい形で厚さが数十mや数百mという小型のものから、大きく発達して頭頂部がカリフラワーのような形になり、雲低から雲頂までの厚さが2000~5000m以上に達するものまでいろいろある。
積乱雲(せきらんうん)
和名:たちぐも
俗名例:入道雲、太郎雲、雷雲、朝顔雲、夕立雲

「垂直に著しく発達している塊状の雲で、その雲頂は山または塔の形を
して立ち上がっている。少なくとも雲の頂の一部は輪郭がほつれるか
または毛状の構造をしていて、普通平たくなっていることが多い。
この雲の底は非常に暗く、その下にちぎれた低い雲を伴い、普通雷電、
強いしゅう雨、しゅう雪、ひょうおよび突風を伴うことが多い」
(気象業務法施工令の定義)
積雲が発達してできた雲で、雲頂部は巻雲などができる領域にまで達している。発達を続けており、頭頂部がカリフラワー状のしっかりとした形を保っているうちは、その雲がいくら大きくても積雲だが、雲頂部が崩れはじめた瞬間から積雲は積乱雲に分類が変わる。
主に水粒の集まりからできているが、雨粒や雪片などが含まれていることがある。雷を伴った強い夕立を降らせる雲である。